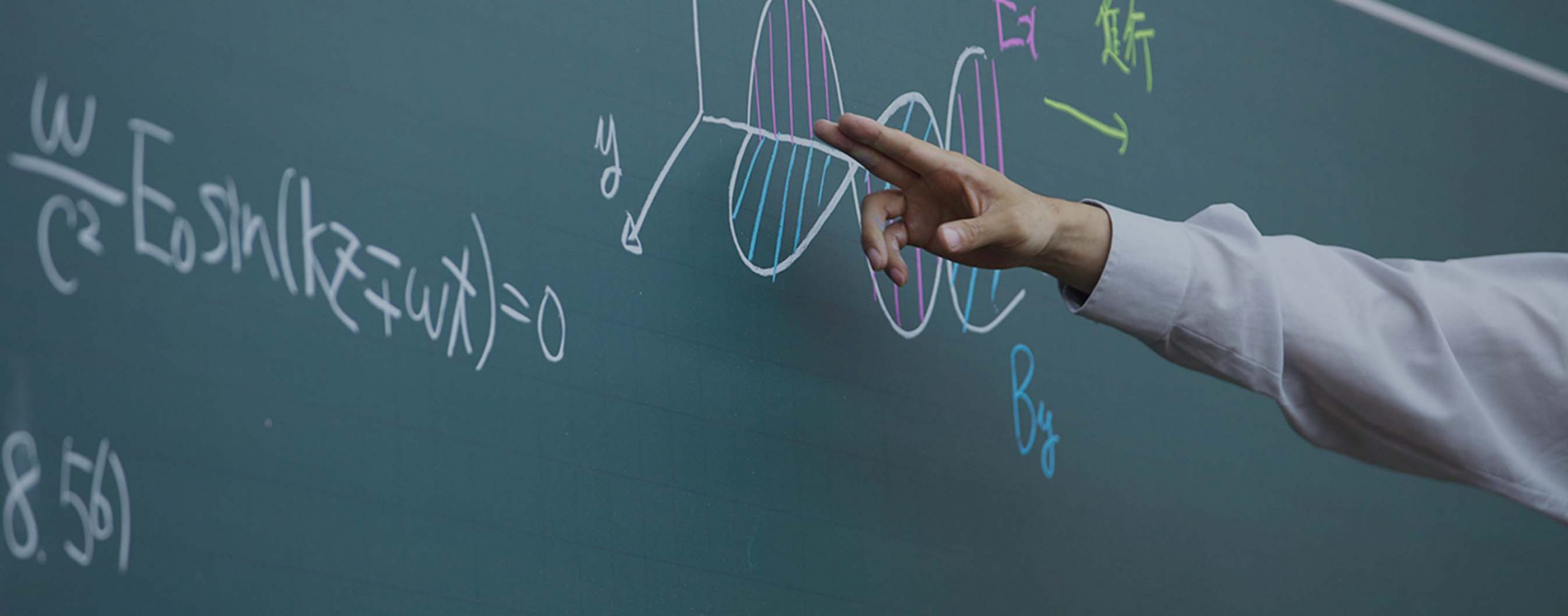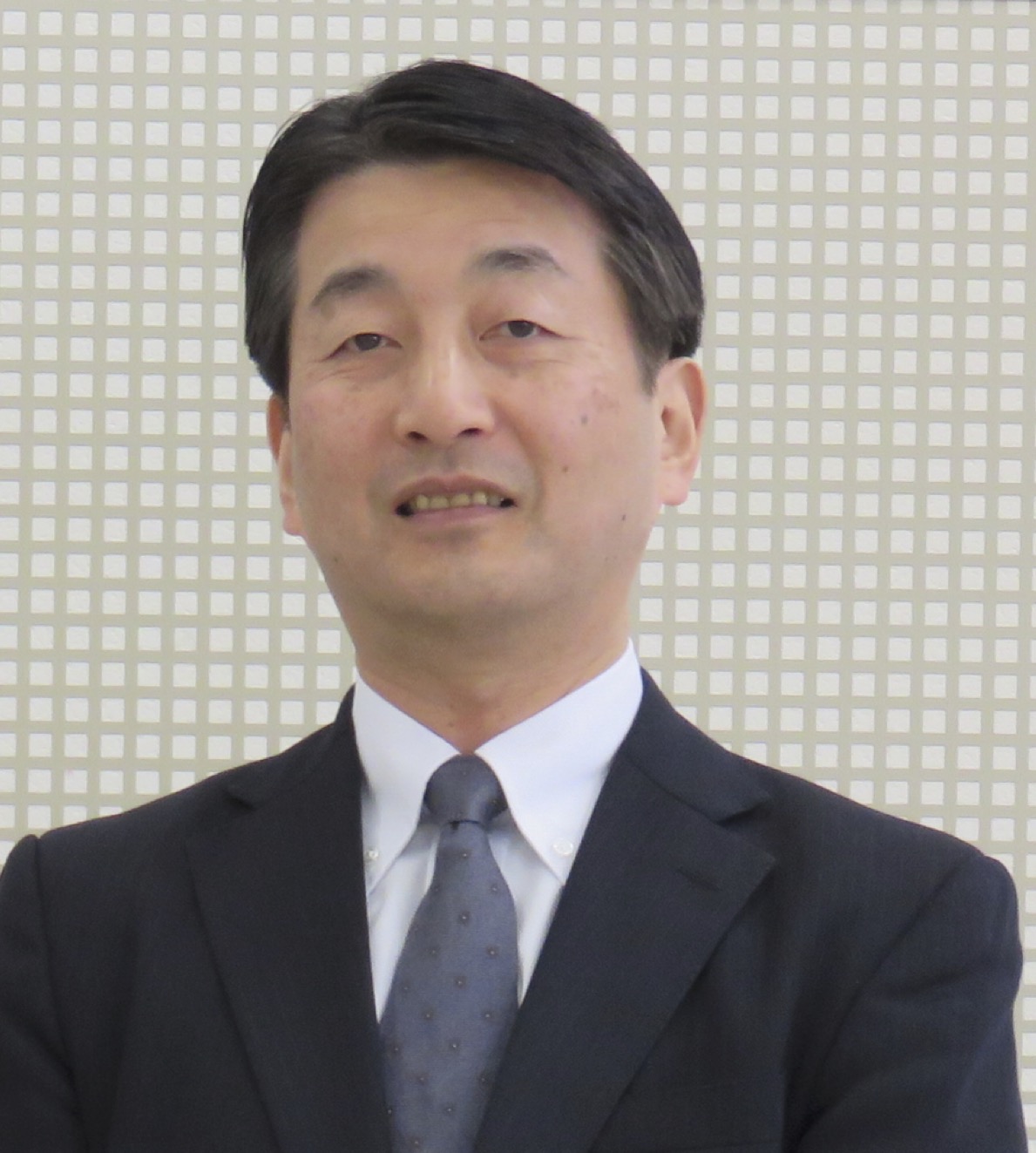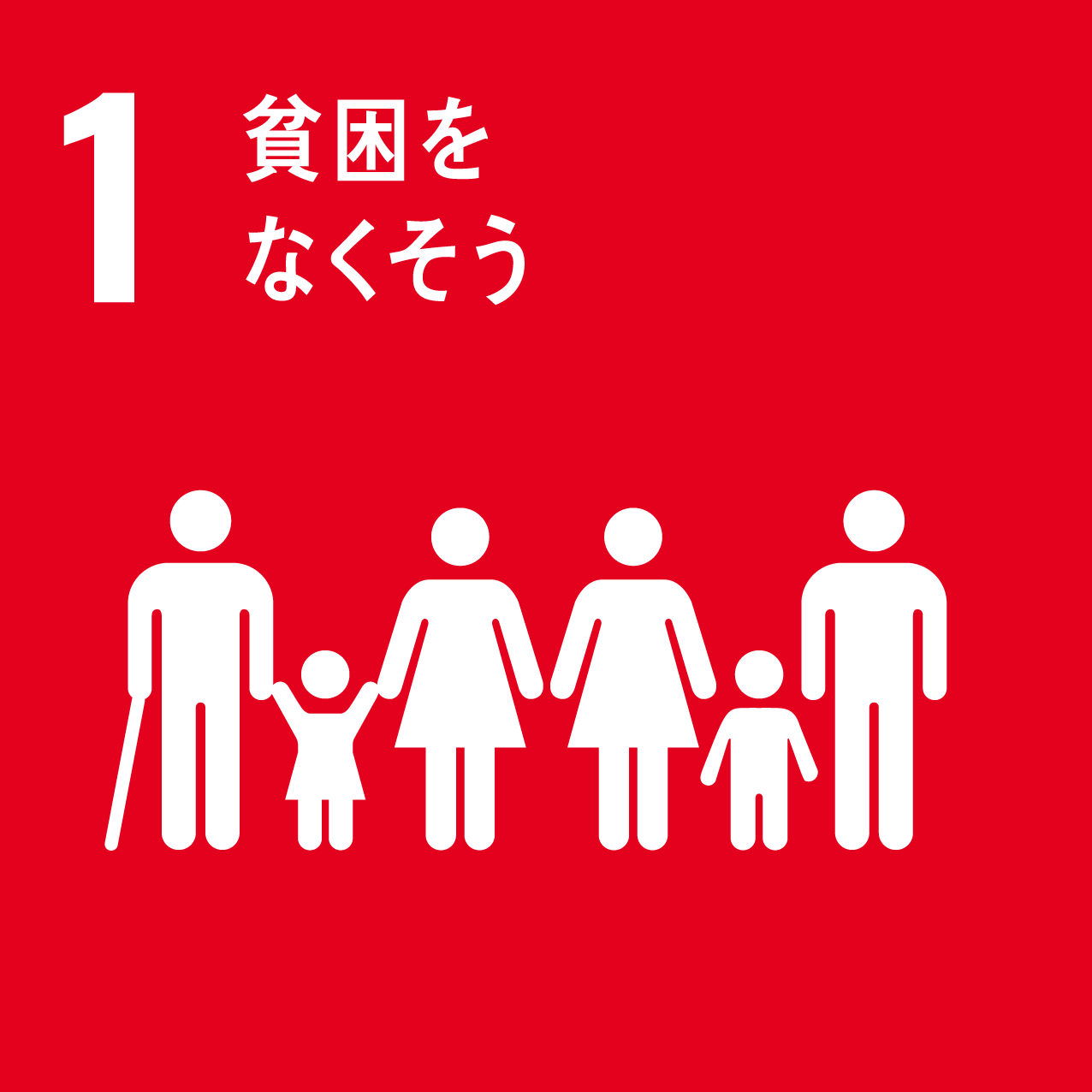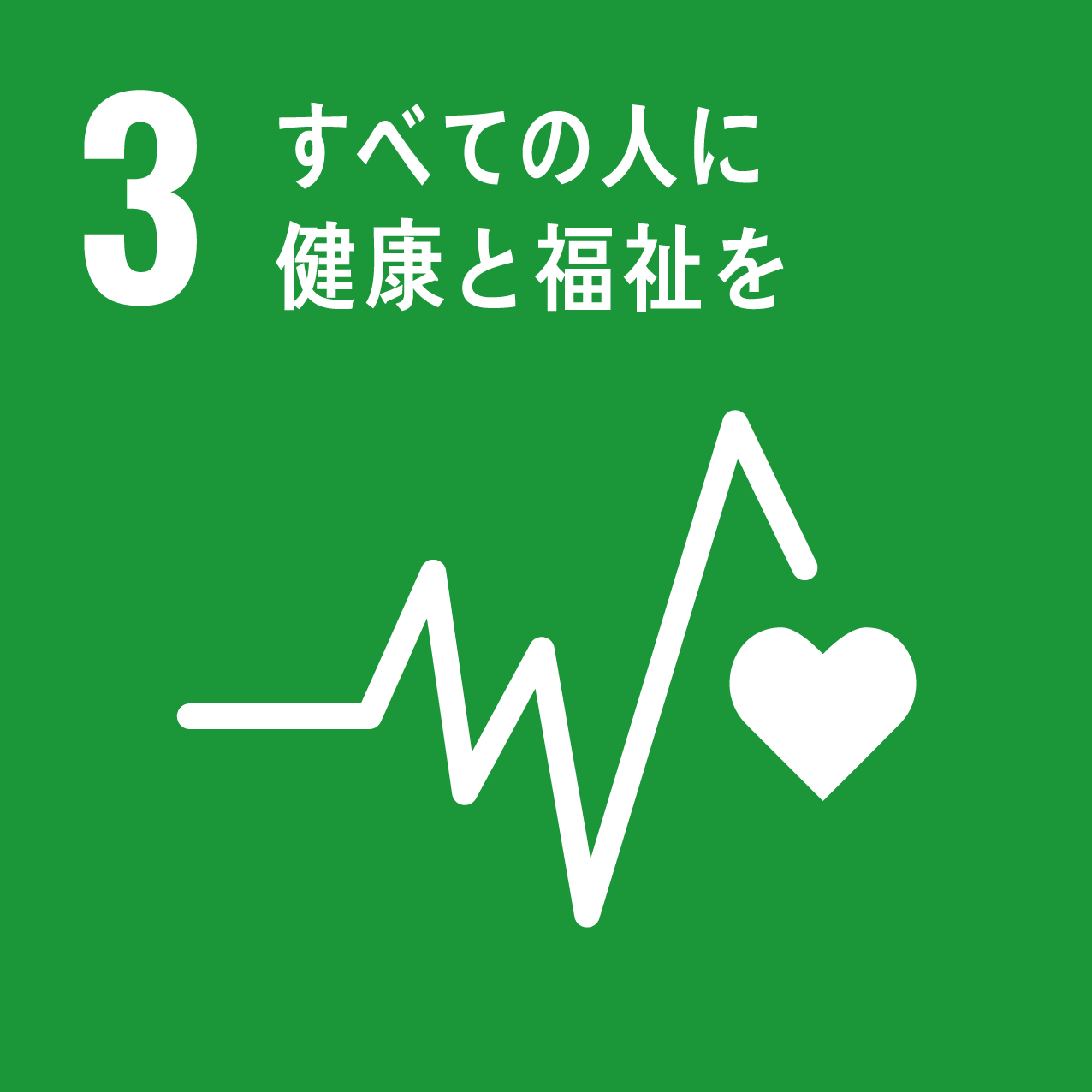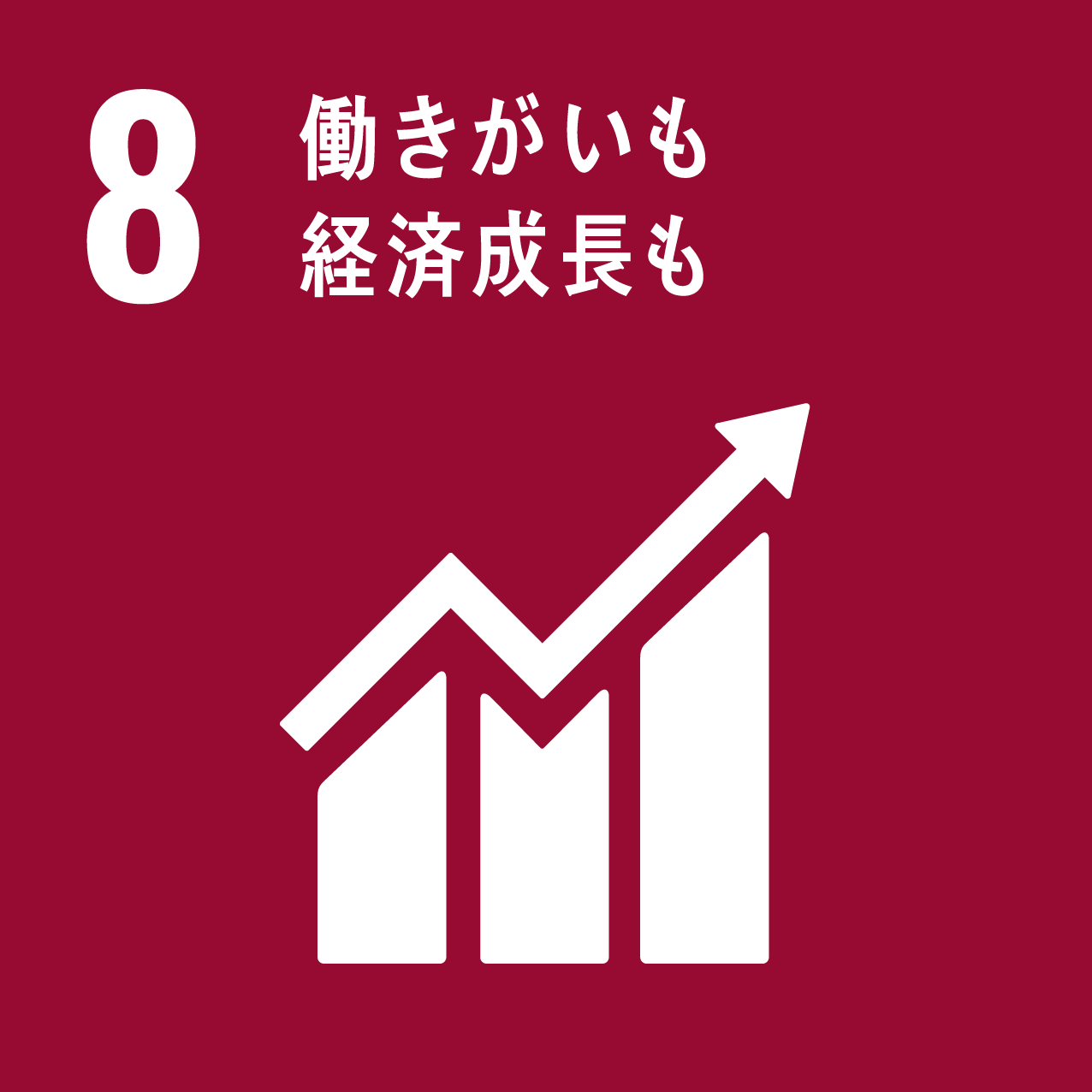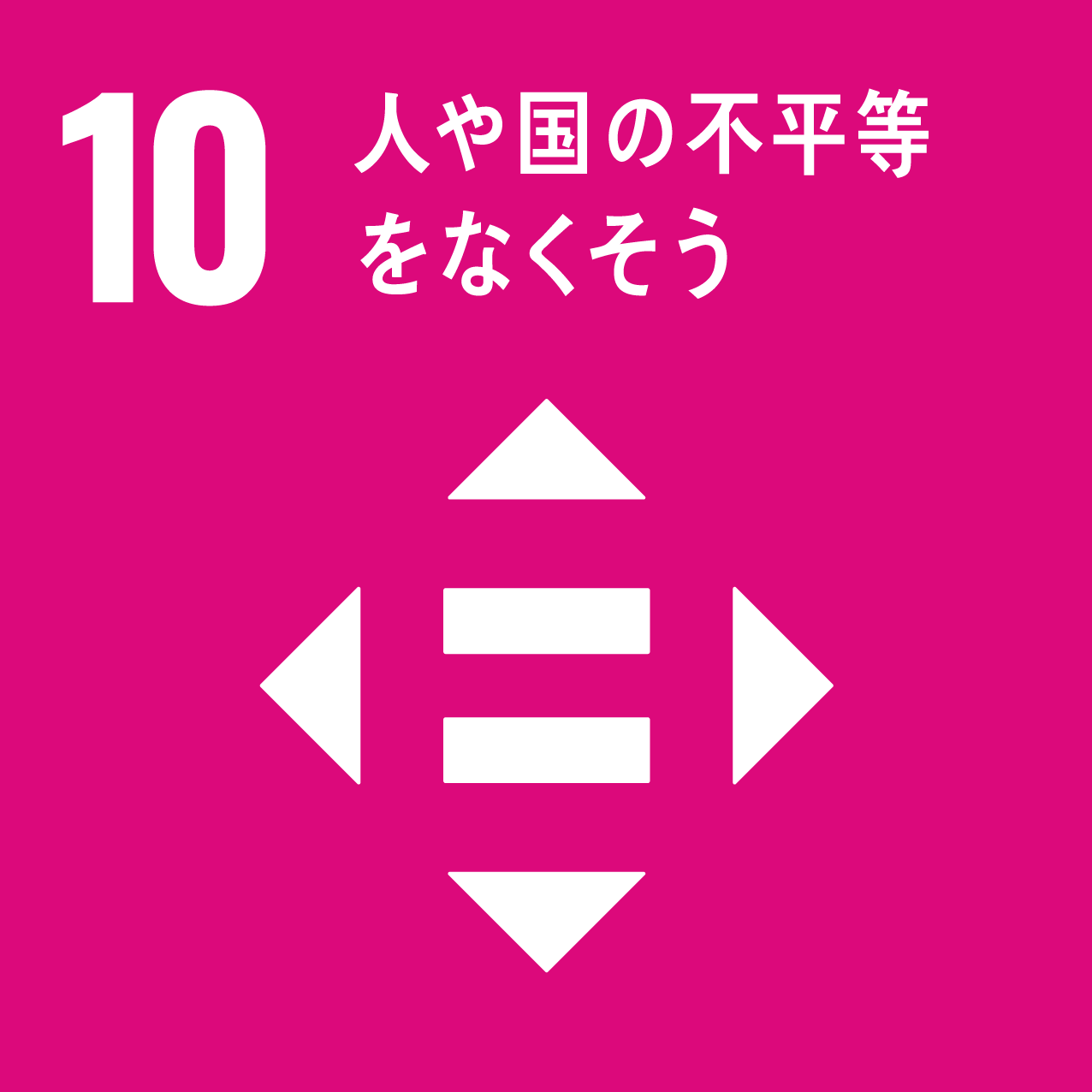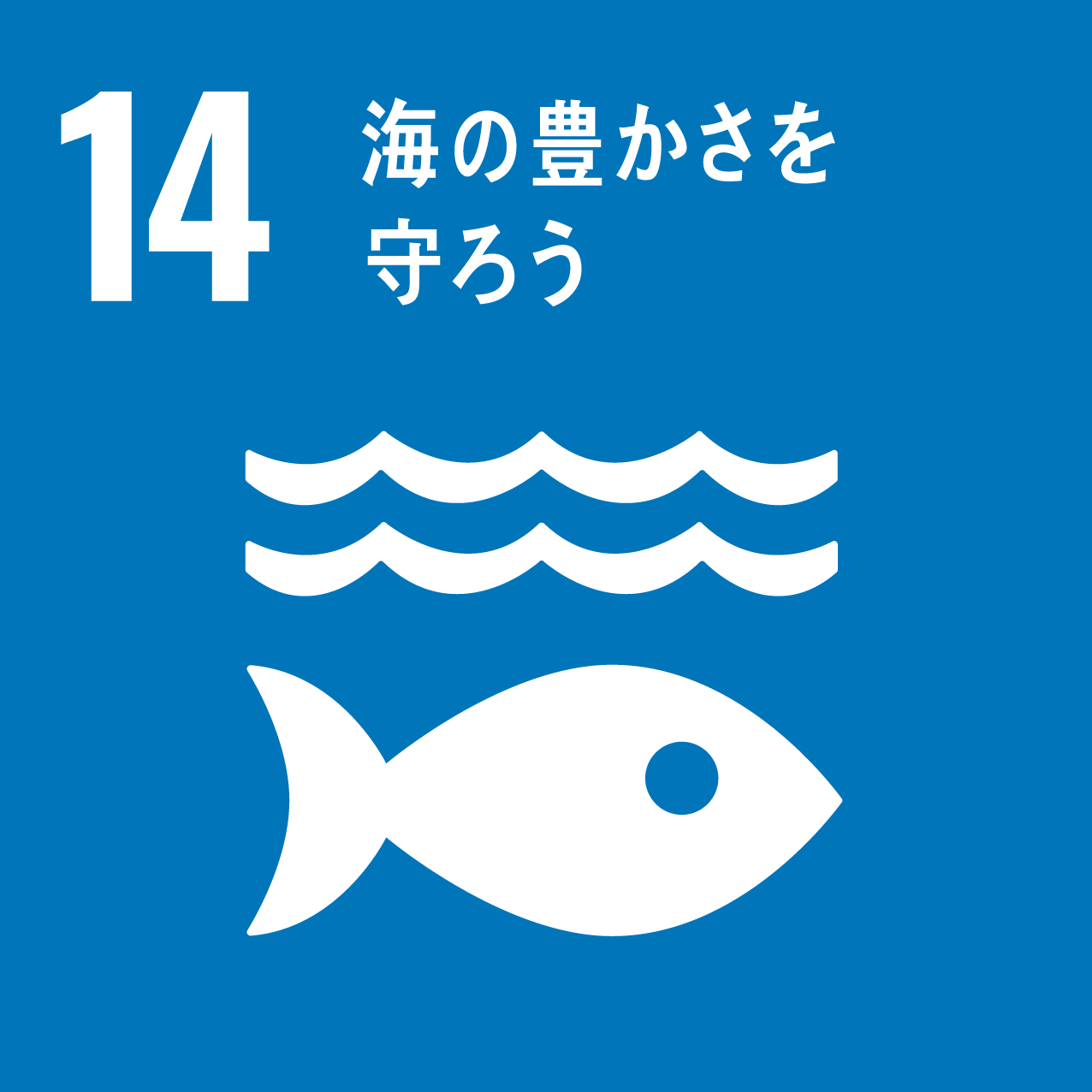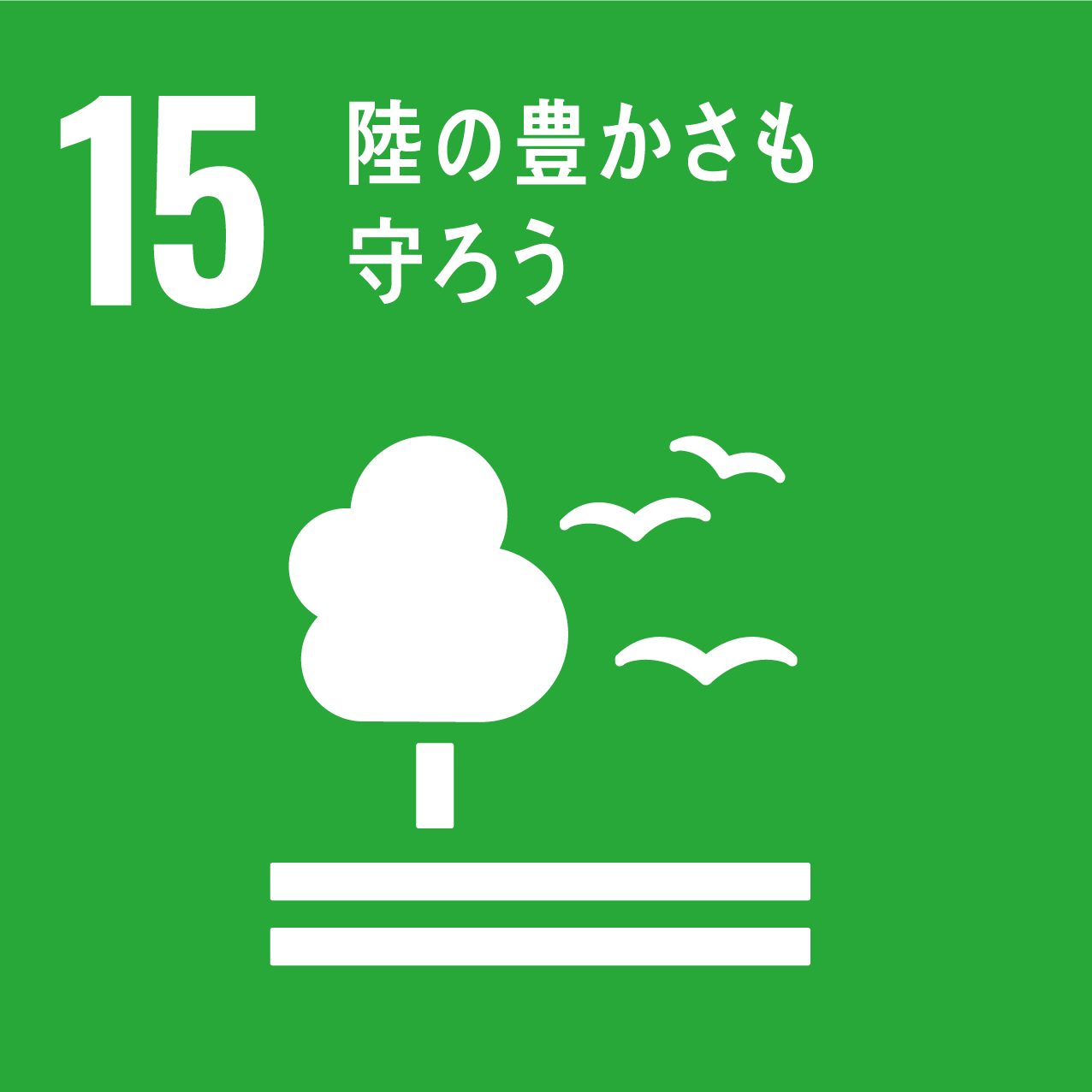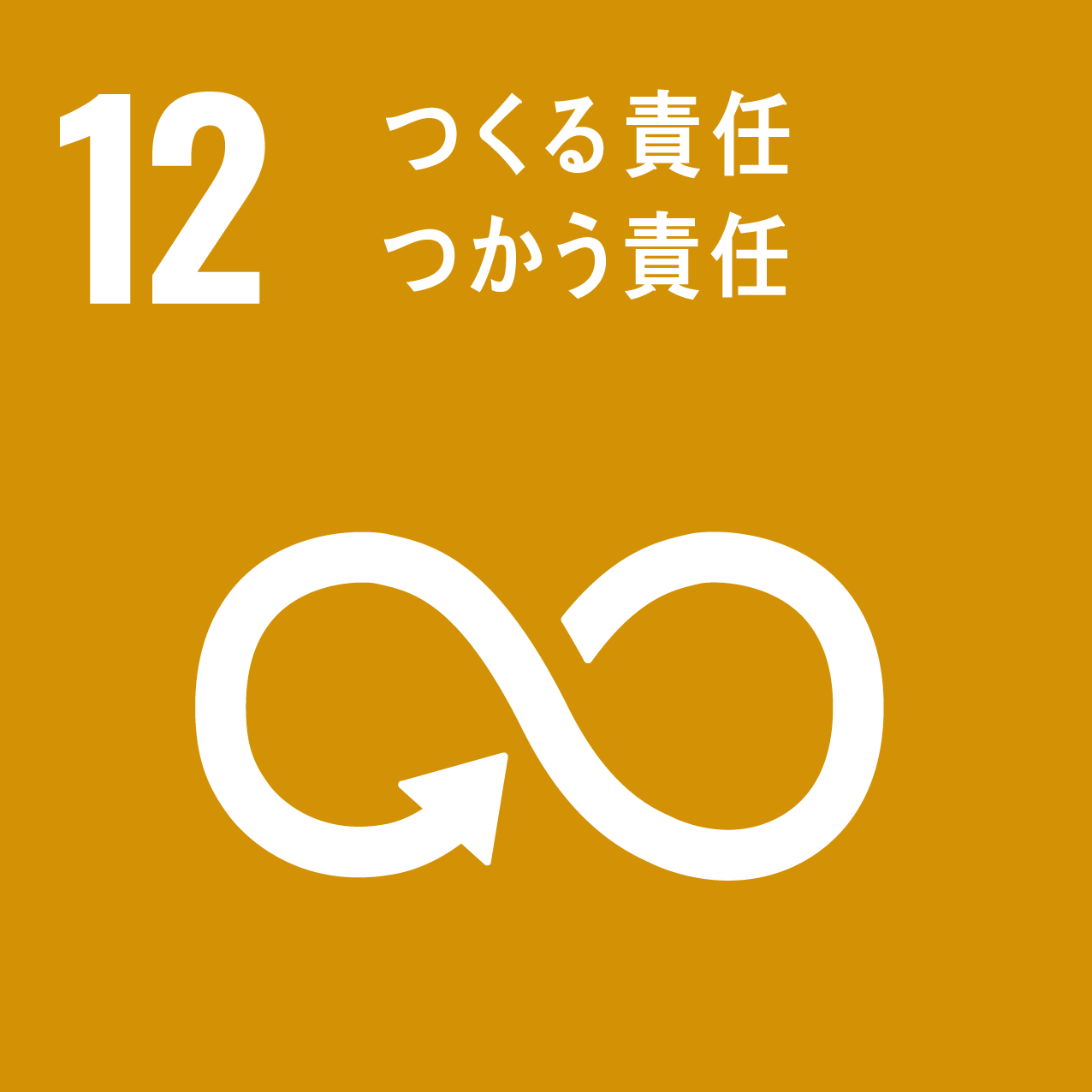⻄原 寛
NISHIHARA Hiroshi 院⻑・教授⻄原研究室
研究室オリジナルHP専攻
物質科学、ナノサイエンス、化学と物理の融合領域
研究キーワード
錯体化学、電気化学、高分子科学、無機化学、ナノサイエンス
SDGsの取り組み
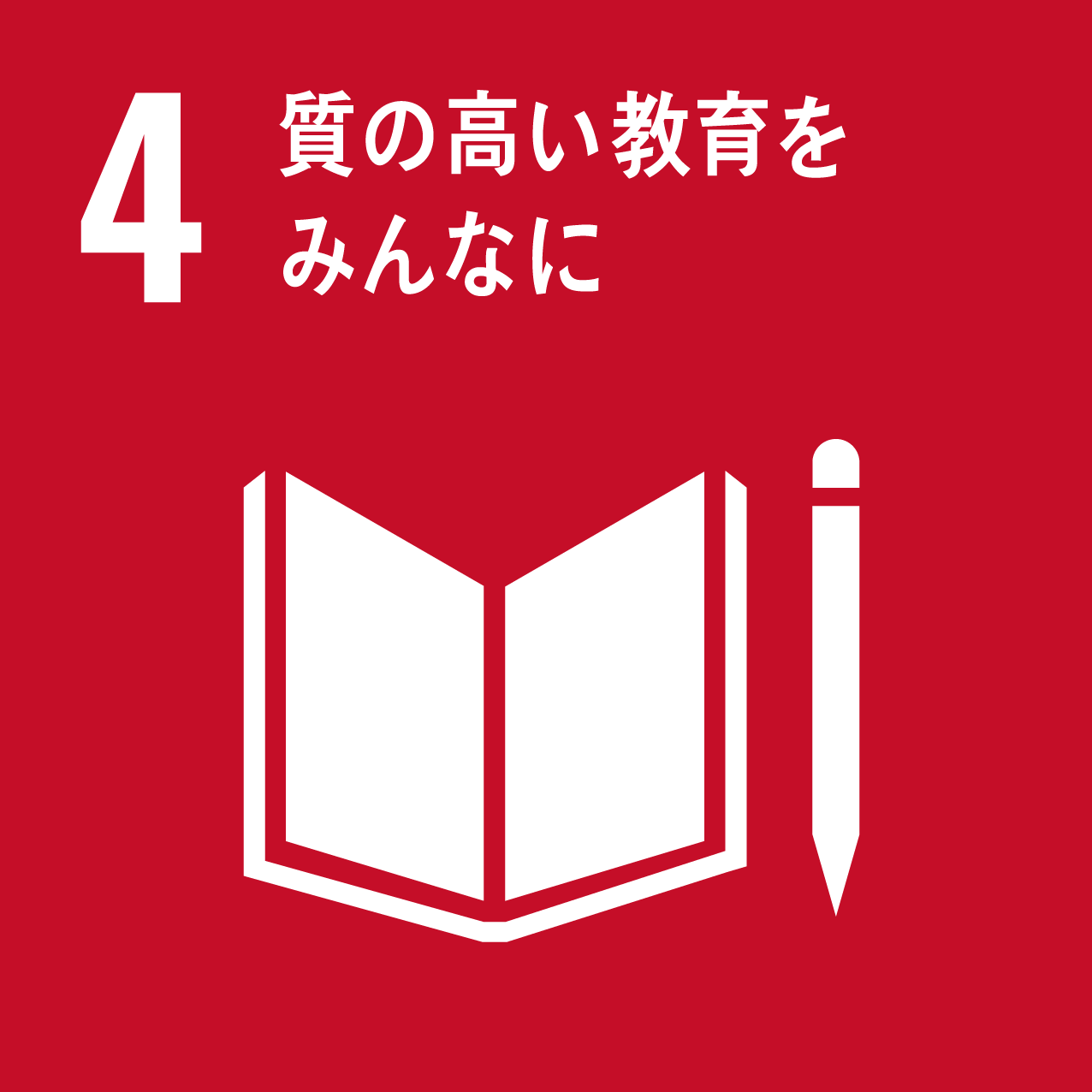
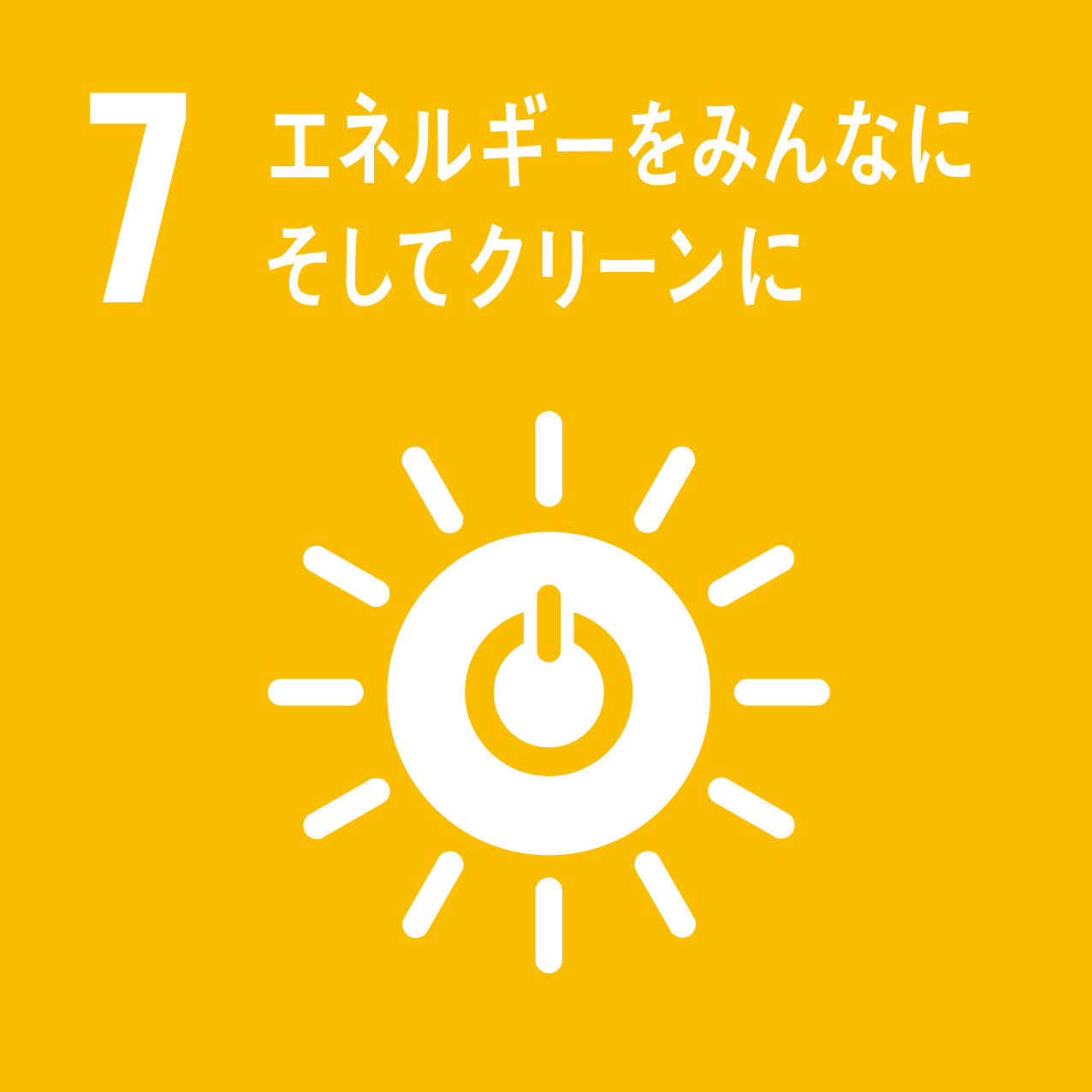
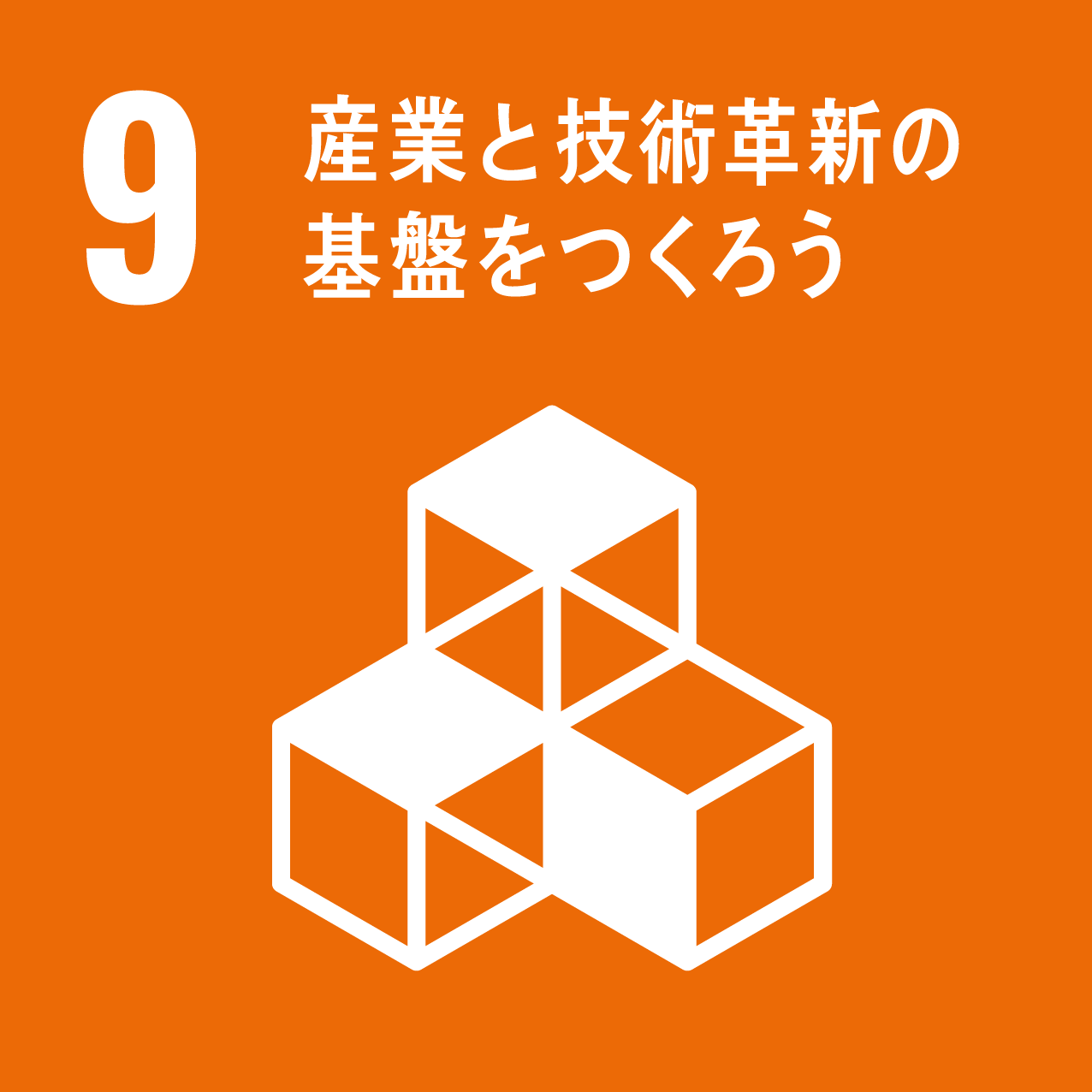

研究内容の紹介
配位ナノシートとは、金属イオンと平面形の架橋有機π配位子との結合で構成される二次元共役ポリマーの極薄膜を指します。金属的な性質を示す配位ナノシートは私たちが2013年に初めて報告しました。配位ナノシートは、金属イオンと有機分子のボトムアップ錯形成反応により温和な条件下で合成できます。
多彩な化学・幾何構造とそれに伴う多様な物性・化学的性質・機械的特性を創出できることから、その科学や産業への波及効果は計り知れません。研究室では、新規機能性配位ナノシートの高品質合成を確立し、物理・化学的特性を明らかにするとともに、ヘテロ積層体・接合体のような複合系を創製してそれらの特異な物理的、化学的機能を導き出し、電子・磁気・光デバイスやエネルギー変換・貯蔵デバイスなどへの応用を探求しています。